

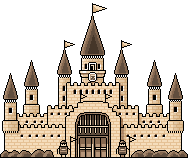
気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!
(印象に残った画像を都度掲載予定です)
<ぶらり皇居> 徳川幕府の居城(江戸城)であったものが、明治元年(1868年)10月に皇居とされ、 翌2年(1869年)3月明治天皇は千年余りの間お住まいであった京都から この地にお移りになり現在に至っています。 徳川幕府の居城であった江戸城は慶応4年(1868年)に明治政府に引き渡され、 半年後の明治元年には明治天皇が京都から江戸へ行幸しました。 江戸は東京、江戸城は東京城と名を改め、翌明治2年の二度目の行幸で 天皇の東京滞在が決まると東京城は皇城と称されることとなりました。 旧江戸城の中心であった本丸及び二の丸の御殿は既に焼失していたため、 無事に残っていた西ノ丸御殿が天皇の御座所として用いられました。 ※久しぶりにリフレッシュできました! |
|
 巽櫓(桜田二重櫓) |
江戸城の時代、本丸から見て東南(辰巳の方角) に位置している事が名前の由来。 江戸城の櫓建設の際に統一して用いられた、 白漆喰塗籠壁などの当時の建材そのままの造り 「石落とし(石垣よりはみ出した出窓部)」 や「(鉄砲、矢用の)狭間」跡からは、当時、 要塞として重要な役目があったこともうかがえます。 |
 大手門 |
旧江戸城の正門で、 大名はここから登城していました。 大手門の高麗門をくぐって中に入ると、 枡形と呼ばれる四角く囲まれた広場になっています。 この枡形は、敵が城内にまっすぐに 侵入するのを防ぐとともに、 攻撃の際には兵の集合場所にもなる施設で、 周囲の白壁には「狭間」という 銃を撃つための穴があります。 江戸城の城門の多くは、この形式でした。 |
 同心番所 |
同心番所には大手三の門を警固する 与力・同心がつめていました。 同心とは、江戸幕府の諸奉行・所司代・ 城代・大番頭などの配下に属し、 与力の下にあって、 庶務・警備の仕事をしていた 下級役人を総称したものです。 同心番所の屋根瓦の一番高いところには、 徳川家の葵御紋の妻瓦があり、 軒先は普通の三巴紋の瓦となっています。 |
 百人番所 |
長さ50メートルを超える百人番所です。 大手三の門を守衛した 江戸城本丸御殿最大の検問所でした。 鉄砲百人組と呼ばれた根来組、伊賀組、甲賀組、 廿五騎組の4組が交代で詰めていました。 各組とも与力20人、同心100人が 配置され、昼夜を問わず警護に当たりました。 |
 大番所 |
大番所は、大手中之門の内側に設けられ、 他の番所よりも位の高い与力・同心 によって警備されていたといわれています。 江戸城本丸へは最後の番所であり、 警備上の役割はきわめて重要 であったと考えられています。 |
 二の丸庭園 |
江戸時代、二の丸には小堀遠州が造り、 三代将軍徳川家光の命で改修されたと 伝えられる庭園がありましたが、 長い年月の間にたびたび火災で焼失し、 明治以降は荒廃していました。 現在の回遊式の庭園は、昭和43年の皇居東御苑の 公開の開始に当たり、 九代将軍徳川家重の時代に作成された 庭園の絵図面を参考に造られたものです。 |
 旧江戸城 天守台跡 |
東御苑北側、本丸広場に佇む石垣は 「旧江戸城 天守台跡」。 この台の上に、 江戸城の天守閣がそびえ立っていました。 現在の国会議事堂程度の高さであった と言われています。 |
 富士見櫓 |
櫓の高さは約16メートルあります。 どこからみても同じような形に見えることから 「八方正面の櫓」とも呼ばれています。 明暦3年(1657)の大火で 天守閣が焼失した後は、 その代わりとされたと伝えられる重要な建物です。 |
 石橋と二重橋 |
皇居正面に見える優雅な石橋で、 江戸時代は西丸大手門橋・西丸下乗橋 と呼ばれていました。 すぐ奥にある橋と石橋の二つの橋で、 二重橋と考えられがちですが、奥の橋が二重橋です。 |
 外桜田門 |
一般には桜田門と呼ばれています。 枡形が完全に残っている城門のひとつで、 小田原街道の始点にあたり、 小田原口ともよばれていました。 扉の釣金具には「寛文三年」の銘が入っています。 万延三年(1860)、大老井伊直弼が この門外の堀端で水戸浪士らに暗殺される 「桜田門外の変」が起きました。 |
 楠木正成像 |
二重橋を正面に見据えるこの像は、 楠木正成公が1333年(正慶2年)隠岐の島から 還幸途次の後醍醐帝を兵庫の道筋で お迎えした折の勇姿を象ったものです。 |